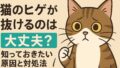猫が念入りに毛づくろいをしながら「ブヒブヒ」「フゴフゴ」と音を立てると、気になって仕方ありませんよね。この記事では「猫毛づくろい ブヒブヒ」というキーワードをもとに、愛猫がこんな音を立てる時の真意や原因をわかりやすく解説します。
ストレス、リラックス、健康面のサインなど、猫が音を立てる背景にはさまざまな心理があります。
本記事を読めば「愛猫の毛づくろいでブヒブヒ言う理由」がきっと見えてきて、安心して接するヒントになるはずです。
- 猫が毛づくろい中にブヒブヒ音を出す理由
- リラックス・ストレス・病気の見分け方
- 飼い主ができるケアと具体的な対処法
目次
猫の毛づくろいでブヒブヒ言う時はストレスが原因?
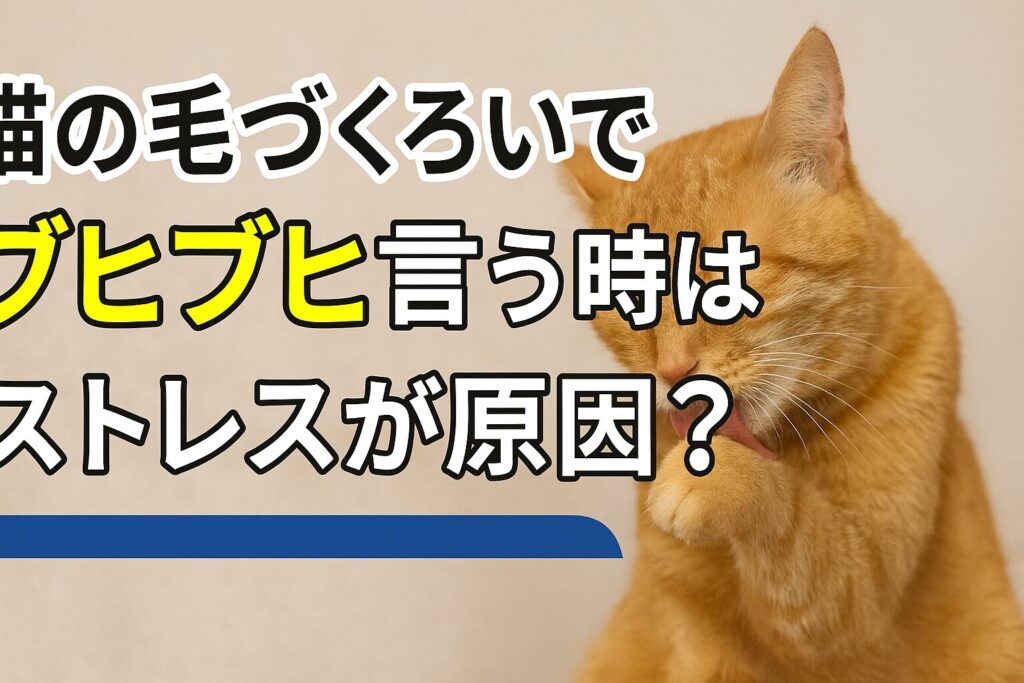
猫が毛づくろいをしながら「ブヒブヒ」と鼻を鳴らすような音を出すと、飼い主としては少し不安になりますよね。
この音の正体は、単なる呼吸音であることもありますが、場合によってはストレスや不安感のサインであることもあります。
まずは音の出るタイミングや様子をよく観察することが大切です。
環境変化や人・動物の出入りによるストレス
猫は非常に環境の変化に敏感な動物です。
引っ越しや模様替え、新しいペットや人が家に来た時など、普段とは違う状況に置かれると強いストレスを感じることがあります。
このようなときに「毛づくろいをしながらブヒブヒ」という行動が見られたら、それは不安のはけ口としてのグルーミングである可能性が高いです。
過剰グルーミングが脱毛や皮膚炎につながるリスク
ストレスが続くと、猫は毛づくろいの頻度や時間が異常に増える「過剰グルーミング」をすることがあります。
これは「転位行動」と呼ばれ、本来のストレス要因を処理できず、別の行動に置き換える心の防御反応です。
長期間にわたってこの状態が続くと、脱毛や皮膚炎のリスクが高まります。
また、鼻息を荒くして「ブヒブヒ」音を伴うのは、呼吸にも力が入ってしまっている証拠かもしれません。
ストレスを感じている猫の他のサインにも注目
ブヒブヒ音とともに、次のような行動が見られる場合は、ストレスを強く感じている可能性があります。
- 隠れて出てこない
- 目が合うとすぐに視線をそらす
- 急に毛をむしるようなグルーミングをする
このような変化に気づいたら、静かな空間を用意したり、生活リズムを整えたりすることが効果的です。
それでも改善しない場合は、早めに動物病院で相談しましょう。
リラックス時にも出る?ブヒブヒ音のポジティブな意味
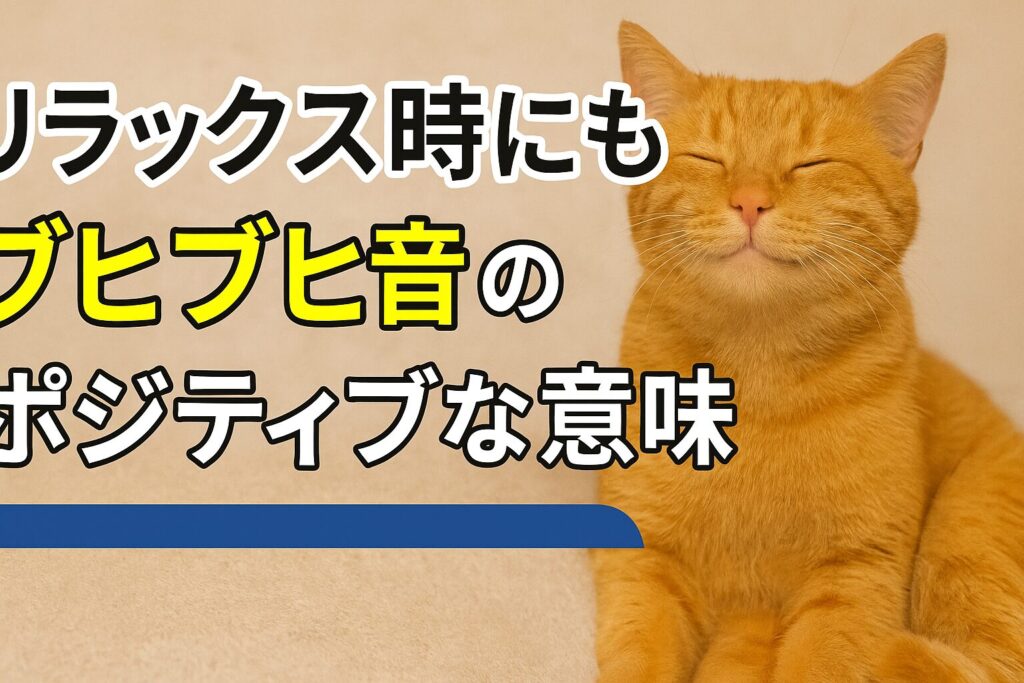
「ブヒブヒ」と聞くとネガティブな印象を受けがちですが、猫にとってはリラックスした状態でもこうした音を出すことがあります。
特に飼い主の前でくつろぎながら毛づくろいをしているときは、安心と信頼の証である可能性が高いのです。
猫の表情や体の緩み具合と一緒に観察すると、その意味が見えてきます。
安心・満足状態での「転位行動」の一種
猫はうれしい気持ちや興奮、または葛藤などの感情を処理する際に、本来とは別の行動で代用することがあります。
これを「転位行動」と呼び、よく見られるのがグルーミングや喉を鳴らすような仕草です。
リラックス時にブヒブヒと音が出るのは、この転位行動の一部と考えられ、気持ちが安定している証拠ともいえます。
飼い主との信頼感が表れるグルーミング時の喉ならし
中には毛づくろいしながらグルグルという喉を鳴らす音が混ざり、それが鼻を通ることで「ブヒブヒ」に聞こえることもあります。
このような音が聞こえる場合、猫は安心しきって気を緩めている状態であり、飼い主への信頼感がとても高いと言えるでしょう。
私の猫も、膝の上で毛づくろいをしながら「ブッ、ブヒ」と小さく鼻を鳴らしますが、その時の顔はとても穏やかで、まぶたが半分閉じているのが印象的です。
顔まわりを重点的に舐めるときに起こりやすい
実際に「ブヒブヒ」という音が出やすいのは、鼻のまわりや口元、目元など顔を重点的に舐めているときです。
このエリアは鼻腔に近いため、呼吸音が響いて「ブヒブヒ」になりやすく、リラックス状態でも物理的に音が出ることがあるのです。
つまり、音自体が問題なのではなく、それがどんな文脈で起きているかが重要ということです。
病気や鼻づまりが原因でブヒブヒ言っている可能性
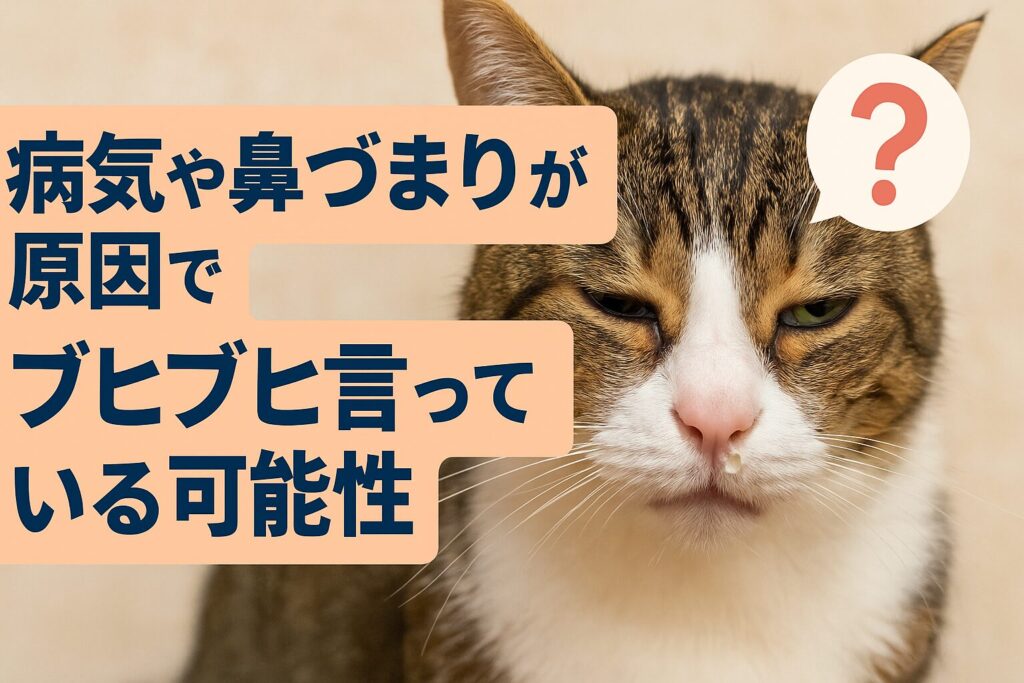
猫の「ブヒブヒ」という音が頻繁に聞こえたり、毛づくろい中以外にも現れる場合、それは健康上の異常サインかもしれません。
特に呼吸器系や鼻のトラブルは、猫にとって深刻な問題になりやすいため、早期の見極めと対応が求められます。
ここでは病気の可能性があるケースについて、具体的に解説していきます。
鼻づまり/副鼻腔炎などで音が大きく聞こえる場合
猫は風邪(猫ウイルス性鼻気管炎)や副鼻腔炎などの影響で、鼻が詰まりやすくなります。
この状態で毛づくろいをすると、呼吸がしづらくなり、鼻の中の空気の振動がブヒブヒと聞こえるような音に変わるのです。
特に「目やに」や「くしゃみ」などの症状が伴っている場合は、ウイルス感染や慢性炎症を疑う必要があります。
異常が続く場合は呼吸音として獣医受診を検討
単発の音であれば問題ない場合もありますが、何日も続いたり、日常的に大きな音を出すようになったら注意が必要です。
猫の呼吸異常は、肺炎や気道狭窄などの重大な疾患が隠れていることもあります。
以下のような兆候がある場合は、できるだけ早く獣医師に相談しましょう。
- 常に口を開けて呼吸している
- 「ヒューヒュー」「ゼーゼー」などの異音がする
- 活動量の低下、食欲不振
また、短頭種(ペルシャやエキゾチックなど)の猫は、鼻腔が狭く呼吸音が元々大きくなる傾向があります。
そうした個体では音が「その猫なりの普通」であることもありますが、普段と違う音質や頻度が見られた場合は注意が必要です。
飼い主ができる「呼吸チェック」の基本
猫の正常な呼吸回数は1分あたり20〜30回ほどです。
眠っているときに胸の上下運動を1分間カウントすることで、呼吸数を把握できます。
急に数が増えた、呼吸が荒くなった、途中で止まりそうになるなど、明らかに異変を感じたら、ためらわず動物病院を受診してください。
実際に見分ける!「ブヒブヒ」の背景別チェックポイント
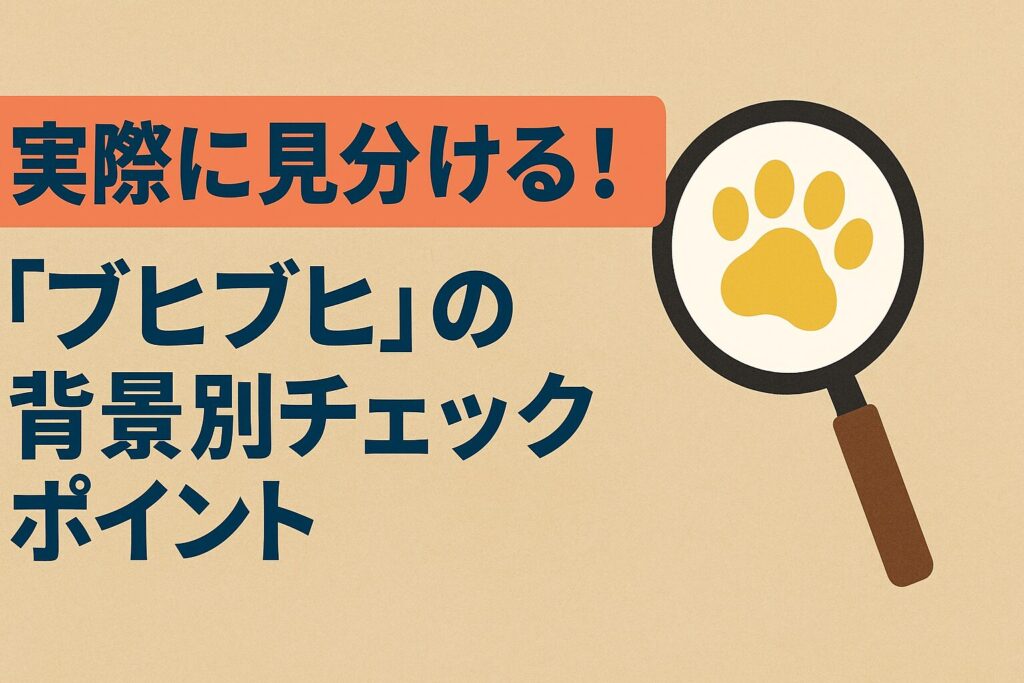
「ブヒブヒ」という音が聞こえた時、すぐに病気かどうかを見分けるのは難しいかもしれません。
ですが、猫の様子や音の出方を冷静に観察することで、その原因をある程度特定することができます。
ここでは、ストレス・リラックス・健康異常の3つの背景別に見分け方のポイントをご紹介します。
ストレス由来なら…ブラッシング頻度や行動の変化チェック
ストレスが原因の場合、猫は毛づくろいの頻度が極端に増える傾向があります。
また、ブラッシングを嫌がるようになったり、自分の毛をむしるような動作が見られたら注意が必要です。
さらに、「目を合わせない」「トイレ以外での排泄」「急に隠れる」などの行動変化があれば、ストレス性のブヒブヒの可能性が高いです。
リラックス由来なら…落ち着いた環境でのみ聞かれる
逆に、飼い主の膝の上やお気に入りの寝床など、安心できる場所でしか音が出ない場合は、リラックスのサインと考えられます。
猫が体を丸めて瞼を閉じていたり、のんびり毛づくろいしている時にブヒブヒ音が出ているのであれば、心配はいりません。
音の出方も比較的短く、規則的ではなく、深い呼吸と共に自然に混ざるような感じであれば、それは安心状態の証拠です。
健康由来なら…呼吸苦しそう・鼻水・口呼吸など他症状とともに
病気や鼻づまりによる場合、ブヒブヒ音は単独で現れるよりも、他の異変とセットで現れるのが特徴です。
例えば以下のような症状が同時に確認できる場合、呼吸器系や感染症の可能性があるため注意が必要です。
- 鼻水やくしゃみ
- 呼吸が早くなる、胸が上下に大きく動く
- 食欲や元気が明らかにない
- 目の充血や目やに
このような兆候がある場合は、早期に動物病院を受診し、原因を特定してもらうことが大切です。
対策法:ストレス・健康・愛情3つのアプローチ

猫が毛づくろい中に「ブヒブヒ」と音を立てる場合、その背景を見極めたうえで適切に対処することが重要です。
ストレス・健康・愛情、それぞれの観点から対策を講じることで、猫の心と体のケアができます。
以下では、原因別にできる具体的なアプローチを紹介します。
① ストレス軽減のための環境整備と遊び時間の工夫
ストレスが原因でブヒブヒ音が出ている場合、猫の安心できる空間を整えることが最も大切です。
高い場所にキャットタワーを設置したり、隠れ家のようなベッドを用意するなど、落ち着けるスペースの確保が効果的です。
また、毎日10分でも遊びの時間をとることで、運動不足と退屈の解消になり、気分転換になります。
② 鼻づまりや皮膚不調には獣医師相談と定期健診を
もし呼吸の異常や皮膚のトラブルが見られる場合は、必ず獣医師の診察を受けましょう。
猫風邪(ウイルス性鼻気管炎)やアレルギー性皮膚炎などは、放置すると症状が悪化しやすいです。
定期健診を通じて早期発見・早期治療を心がけることで、長期的な健康維持にもつながります。
③ ブラッシング・スキンケアで清潔維持+コミュニケーション強化
猫にとって毛づくろいは大事な日課ですが、被毛の絡まりや皮膚炎があると負担になります。
定期的なブラッシングで抜け毛を取り除き、スキンシップを通じて猫の状態をチェックしましょう。
ブラッシング中に猫が気持ちよさそうに目を細めていれば、それは信頼の証です。
この時間を利用して健康状態の変化も感じ取れるようになれば、飼い主としてのケア力も自然と高まります。
まとめ:「猫毛づくろい ブヒブヒ」は愛情と健康のバロメーターまとめ
猫が毛づくろい中に発する「ブヒブヒ」という音は、一見すると不安を感じさせるかもしれません。
ですが、その背景にはリラックス、信頼、ストレス、病気など、さまざまな心理や身体の状態が隠れています。
その音の意味を正しく読み取ることで、猫との関係性もより深まります。
まず、落ち着いた環境でしか音が出ない場合は安心の証と捉えて大丈夫です。
逆に、頻繁に音を立てたり、他の異常行動とセットになっている場合は、ストレスや体調不良のサインの可能性があります。
音そのものよりも、「いつ」「どんな状況で」「他にどんな変化があるか」を観察することが何より重要です。
そして、飼い主としてできることは、猫の変化を見逃さず、環境を整え、必要があれば専門家に相談すること。
その積み重ねが、猫にとっての安心や健康につながり、結果としてブヒブヒ音すらも「愛されている証」と感じられるようになります。
猫の毛づくろいとブヒブヒ音は、あなたと猫の関係を映し出すバロメーターなのです。
- 猫が毛づくろい中に出すブヒブヒ音の原因を解説
- 音の正体はリラックス・ストレス・病気の可能性
- 呼吸音やグルーミング行動の変化にも注目
- 飼い主による観察と早期対応が重要
- 環境づくりや遊びの時間でストレス軽減を
- 鼻づまりや異音が続く場合は病院受診を検討
- 信頼関係を深めるブラッシングやケア方法も紹介